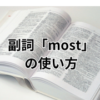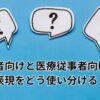知っているようで知らない「助詞」:前編
新年あけましておめでとうございます。
2024年も皆さんにとって明るく楽しい年になりますように!
さて、新しい年の幕開けで、やる気が満ち溢れているうちに、ちょっと敬遠されがちな「助詞」について、お話しようと思います。 翻訳されたものを含め、文章の校正のプロセスでは「てにをはの使い方がおかしい」という指摘がなされることがありますが、この「てにをは」が助詞です。皆さんは、どのくらい自信をもって助詞を使っていますか?「なんとなく」「どちらかというと」「気持ち悪くない方」なんて感覚的な使い方してませんか?私は、まごうことなき感覚派です。この感覚的な助詞を整理して、少しでも分かりやすくなるよう体系的にまとめてみました。長くなってしまうので、前編と後編に分けています。この記事が少しでも皆さんのお役に立ちますように。
助詞の説明と分類
助詞とは、別の自立語(単独でも文節を構成することのできる語)に付属して、意味を添えたり、自立語間の関係を示したりする、活用しない(=形が変わらない)語です。
助詞には次の4種類があります。
- 格助詞:主に体言(=名詞など)に付いて、その体言とそれに続く語句との関係を示します。(例:が、を、に、へ、と、より、から、で、や、の)
- 副助詞:さまざまな語句に付いて、意味を加えます。(例:は、も、こそ、さえ、でも、ばかり、など、か)
- 接続助詞:主に活用する語句に付いて、前後の文節をつなぎます。(例:ながら、ば、と、ても、が、けれど、けれども、のに、ものの、ところで、ので、から、し、たり、て)
- 終助詞:文や文節の最後に付いて、話し手・書き手の気持ちや態度を表します。(例:か、な、ね、よ、ぞ、とも、なあ、や、わ、ねえ)
※助詞の分類は文法の研究者によって異なります。ここでご紹介しているのは日本の学校で教える、いわゆる学校文法に基づくものです。
以上が助詞の体系的な説明ですが、本記事では助詞ひとつひとつを説明するのではなく、上記の助詞のなかでも特に使い方や使い分けが難しいものをピックアップして、解説していきます。
格助詞「が」と副助詞「は」
最も感覚的に使っているキングオブ悩ましい助詞が(は?)、「が」と「は」であることは議論の余地がないですよね。この一文でさえ、「悩ましい助詞が」なのか「悩ましい助詞は」なのか悩みます。そこで、ここでは「が」と「は」のそれぞれの用法を解説し、その使い分けを見ていきます。
<「が」の基本的な用法>
格助詞「が」の基本的な用法には、「眼前描写」と「選択指定」があります。
眼前描写(中立叙述):出来事を見たまま、聞いたままに表現します。そのため臨場感があります。また、特別な意味を感じさせない中立的表現です。(例:バスが来た。)
選択指定(総記/排他):複数の候補の中から何かを選び取る表現です。したがって、結果的に排他性が表されます。(例:「どの果物を買う?」「ミカンがいい」→いろいろな果物がある中でミカンを選択しています。それにより他のリンゴやブドウは排除されています。)
<「は」の基本的な用法>
副助詞「は」の基本的な用法には、「主題提示」と「対比」があります。
主題提示:「~について言うと」や「~に関して言えば」という意味合いで使われます。(例:象は鼻が長い→「象について言うと(主題提示)」「鼻が(眼前描写)」「長い」
対比:複数のものを対比させる表現です。(例:おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。)
なお、1つの文に「は」が2回出てくるときもあります。(例:彼は、肉は食べない→1つ目の「は」が主題提示で、2つ目の「は」が対比です。)
<「が」と「は」の使い分け>
以上、「が」と「は」のそれぞれの基本的な用法を見ていきました。ここからは、それぞれの使い分けを解説します。「『が』と『は』どっちを使ったらいいの~!?」と悩むことありますよね。その場合以下の方法に従って使い分けてください。
使い分け方1:新情報か旧情報によって分ける-新情報には「が」、旧情報には「は」
会話の中や文脈で、主格が未知(=新情報)の場合は「が」を使って表し、既知(=旧情報)の場合は「は」を使って表します。
例:Aさん:「ハワイはどうだった?」(旧情報)Bさん:「海がキレイだったよ」(新情報)
→Bさんがハワイに行ったことが、AさんとBさんの両方にとって既知のため「ハワイは」と「は」を使っています。Bさんは「海がキレイ」という未知の情報を伝えているため「が」を使っています。
使い分け方2:現象文か判断文によって分ける-現象文には「が」、判断文には「は」
「現象文」とは文字どおり、現象をありのままに、話し手の主観的な判断を加えずに表現する文です。現象文には「が」をつけます。これに対して、現象に対して話し手が主観的な判断を加えて表現する文を「判断文」と呼びます。判断文には「は」をつけます。
例1:雨が降った(現象文)
例2:雨は嫌いだ(判断文)
使い分け方3:主格が節に係るか、文に係るかによって分ける-節のみに係るときは「が」、文末まで係るときは「は」
例1:彼が昨日食べたパンは、カビが生えていた。(「彼が」は「食べた」に係り、「生えていた」に関係しない)
例2:彼は、昨日カビの生えたパンを食べた。(「彼は」は「食べた」に係る)
使い分け方4:排他か対比によって分ける-排他のときは「が」、対比のときは「は」
「それだけが」「他ならぬ~」という排他の意味を持つときは「が」を使用し、「比べて言うと、〜である」という対比の意味を持つときは「は」を使用します。
例1:私がリーダーだ(他の者ではなくて、私だけがリーダーであるという排他の意味を表す)
例2:犬は好きだが、猫は嫌いだ。(対比)
使い分け方5:措定文か指定文によって分ける-措定文には「は」、指定文には「は」か「が」
措定文(そていぶん)とは「述語が主格の性質を表わす」文のことです。判別する方法としては、「AはB」とした場合に「BはA」が成り立たない場合、措定文ということができます(例:チワワは犬だ。→×犬はチワワだ。したがって、措定文)。措定文では「は」を使用します。
これに対して、「指定文」とは、述語が主格と同じものであることを示す文です。指定文ではAとBを逆にしても成り立ちます。(例:「鈴木さんはあの人だ」→「あの人が鈴木さんだ」のように言い換えられます。「鈴木さん」=「あの人」です。)指定文では「は」も「が」も使用します。
さて、最初の方に記載した「最も感覚的に使っているキングオブ悩ましい助詞が(は?)、「が」と「は」であることは議論の余地がないですよね」の一文では「悩ましい助詞が」がいいのか、「悩ましい助詞は」がいいのか、どちらでしょうか?「悩ましい助詞」を「主題」だと捉えれば「は」となり、「排他」と捉えれば「が」となりますが、今回私は「キングオブ悩ましい助詞こそが」と排他の意味を強調したいので「が」を選択するのがよいと判断します。
おわりに
新年早々情報を詰め込んで長くなってしまいましたが、ここまでお読みいただきありがとうございました。2024年5月にUP予定の後編では、「が」「は」以外の助詞をご紹介します。
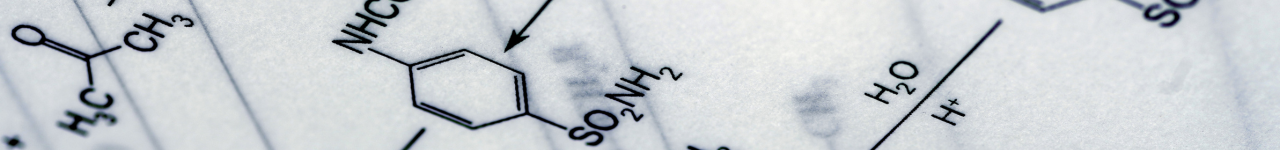
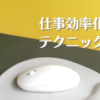
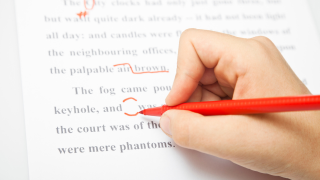

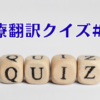




-100x100.png)