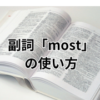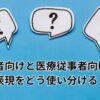納品時の「コメント」
翻訳作業が訳文だけで完結すればそれに越したことはないのですが、ときに翻訳者さんから翻訳会社やクライアントに対して注意を喚起したり、申し送りをしたりする必要が生じます。こうした注意喚起や申し送りを、MTSでは翻訳物に付随する「コメント」と呼んでいます。
この記事では、翻訳会社が受け取って嬉しいコメントと、そうでもないコメントについて私見を述べたいと思います。
原文の記載が誤りと思われる場合(嬉しい度:★★★★☆)
コメントの例
『製品名/内容/数値が誤っているように思われます。ご確認ください。』
・「製品名が異なる」(例:製品Aの試験のはずが、製品Bとなっている箇所がある)
・「内容が矛盾する」(例:非盲検試験のはずが、無作為化に関する記述がある)
・「数値が誤っている」(例:全体の患者数と、内訳の合計が一致しない)
これは、個人的にうれしや、ありがたやなコメントです。原文が仮に不適切でも、その内容が訳文にそのまま反映されていれば、翻訳という作業の本来の義務は果たしていると言えます。しかし、上記のような原文の誤りを指摘することができれば、クライアントにとって付加価値になると考えられます。また、翻訳会社としても、言葉を機械的に置き換えるのではなく、きちんと内容を吟味して翻訳していただけているということが端的に伝わってくるので、とても好印象です。
クライアントや翻訳会社から準拠を求められた参考資料の内容に疑義があるときも、同じようにコメントしていただけるとありがたいです。
なお、このような場合に『原文の誤りだと判断して訳文では修正しています』というコメントをしてくださる方もいます。それも悪くはないのですが、数値や記載が一見誤っているように見えて、実は何らかの事情で正しいということや、間違っていても原文通りにしたい(=英語版と日本語版が一致することを優先したい)ということもわりとあるため、原文通りに翻訳しつつコメントで疑義を指摘していただく形がより望ましいです。
原文から離れた訳をしている場合(嬉しい度:★★★☆☆)
コメントの例
『原文は○○ですが、内容を踏まえて××としています』
これもあると嬉しいコメントです。一見すると訳文が原文から離れているように思われる場合(例:原文に対して言葉が少ない・多い)、チェッカーが翻訳者さんの意図を汲めずに逐語的に修正してしまう可能性があります。そうでなくても、その意図を理解するために、通常よりも多くの時間を確認にかけることになります。上記のようにコメントしていただけると、せっかく工夫していただいた訳文を損なうことがなくなり、チェッカーの負担も減るので大変助かります。
特に、原文が悪文で、文法的に破綻していたり、イレギュラーであったりして、そのまま翻訳することはできない場合、どのように判断してその訳に至ったのかをコメントに記載していただけると、とてもありがたいです。
翻訳の参考とした情報の引用(嬉しい度:★★☆☆☆~★★★☆☆)
コメントの例
『以下を参考に翻訳しました。http://…..』
これはありがたい場合もあれば、そうでもない場合もあるコメントです。国際規格やガイドライン、法令などの正式な名称や、日本人の氏名の読み(英訳の場合)や漢字表記(和訳の場合)について、典拠を示してくださるのは確認がしやすくなるので助かります。
ただ、数10ページもある資料を翻訳の根拠としてご提示いただき、しかも文書内検索ができないような場合、ご参考にされた箇所を特定するだけで多大な労力が必要となってしまい、確認をあきらめることさえあります。
また、これは「コメントの内容」というテーマから少しずれますが、翻訳対象の文と完全に又は部分的に合致する日英対訳をウェブ上で見つけていただいて、『こちらの訳を流用しています』とコメントいただくこともありますが、流用元の訳の質が低く顧客への納品に堪えない場合や、翻訳対象の文と細かい点で差異があり、手直しが必要になる場合などがあります。コメントつながりで、ご注意いただきたいと思います。
原文の解釈に自信がない場合(嬉しい度:★☆☆☆☆)
コメントの例
『この箇所の解釈に自信がありません』『この単語の定訳が不明でした』
これはいただいても、どちらかというと困ってしまうタイプのコメントです。個人差はありますが、基本的に翻訳の実力は「翻訳者さん>チェッカー」なので、翻訳者さんが解釈しきれなかったり、適訳にたどり着けなかったりした場合に、チェッカーにリカバリーを期待するのは、なかなかに酷です。
普段、そうしたコメントをしない方が、「どうしてもこれだけは分からない……」という苦渋の思いでつけてくださるのであれば、チェッカーとしてもその箇所にできる限り力を入れて見るようにしよう、となりますが、このようなコメントをつけることが習慣化してしまい、1ページで何ヵ所も『分かりませんでした』とお伝えいただいても、受け取る側にとってはコメントの意義があまりありません。
まとめと注意点
以上、翻訳物を納品する際のコメントについて、簡単にまとめてみました。こうしたコメントはつけなくてもマイナス評価につながることはありませんが、つけていただければ翻訳者さんにとっては評価アップ、翻訳会社にとっては作業負担の軽減、エンドクライアントにとっては翻訳物の価値の向上と、すべての関係者にとって有用なものとなる可能性があります。
ただし、コメントをつけるという行為は、それなりに時間を取るものです。ですので、私は「絶対にコメントをつけてくれ!」というようなことは決して言いません。それぞれの方が適切と考える程度につけていただければ、翻訳会社としては御の字です。翻訳をしていてコメントをつけようかどうか迷われた際、この記事がいくばくかのご参考になれば幸いです。
最後までお読みいただき有難うございました。
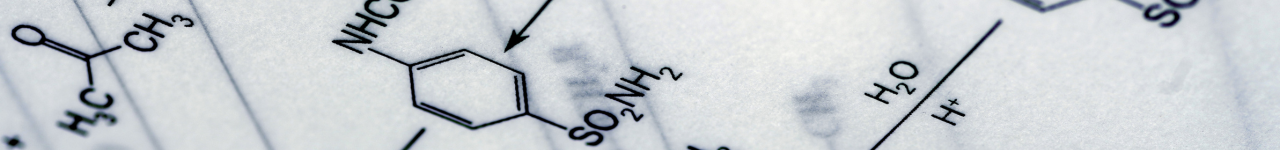
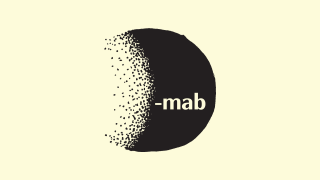




-100x100.png)


-100x100.png)