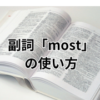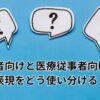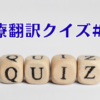薬ができるまでと発生する翻訳文書~承認申請・製造販売編①~
前回の「薬ができるまでと発生する翻訳文書~臨床試験(治験)編~」では、臨床試験(治験)段階で発生する文書についてご紹介しました。今回は、「承認申請・製造販売」で発生する文書をご説明します。こちらもボリュームが多いため、2回に分けてお届けします。承認申請関連文書は重要度・難易度がともに高く、翻訳の精度が特に求められます。今回もコーディネーターならではの視点を交えてお伝えしますので、ぜひご覧ください。
臨床試験(治験)編はこちら
🔻
https://blog.m-t-s.jp/drug-development-documents2/
承認申請・製造販売
この段階では、企業(製薬会社や医療機器メーカー)がPMDA(医薬品医療機器総合機構)に申請を行い、審査を経て厚生労働省の承認を受けます。その後、製造・販売を開始します。
承認申請段階で発生する文書
機構相談用資料:
「機構相談」とは?
PMDA(医薬品医療機器総合機構)は、厚生労働省所管の独立行政法人で、医薬品や医療機器等の承認審査をはじめ、申請資料の信頼性調査や製造体制の確認など、開発初期から製品販売後まで幅広く関わる機関です。この中で企業が行う申請前の相談を「機構相談」と呼びます。
「機構相談用資料」とは、その名のとおり、機構相談の際に使用される文書です。例えば以下のものがあります。
機構相談資料(briefing document/briefing book)<ブリーフィングドキュメント(BD)/ブリーフィングブック(BB)>:企業がPMDAに提出する薬剤の概要や試験結果、相談事項などがまとめられた資料で、クライアントのグローバル(日本国外の本社/支社)で作成された英語文書を日本語に翻訳するため、基本的に和訳のみが発生します。分量も多く、提出期限も決まっているため、複数名での分担が一般的です。
照会事項:治験届や申請資料提出後にPMDAから送られる質問です。これに対しては必ず回答が必要です。まずは、英訳後グローバルに共有し、返答後は和訳が発生します。PMDAから照会事項は発出時期が読みにくい一方で、回答には期限があるため常に時間勝負です。品質も非常に重要で、回答に不明な点があると追加照会となってしまうため誤訳も許されないハードな案件ですがポイントを押さえれば大丈夫です!
コモン・テクニカル・ドキュメント(Common Technical Document)<CTD>:日米EU共通の医薬品の承認申請資料で、ICH(日米EU医薬品規制調和国際会議)により標準化されたフォーマットです。以下の5つから成ります。
- モジュール1:日米EUそれぞれ独自の申請書や添付文書
- モジュール2:CTDの概要
- モジュール3:品質に関する文書
- モジュール4:非臨床試験報告書
- モジュール5:臨床試験報告書
分量が多く申請日が決まっているため、納品までに余裕があることはありません。特に記載ルール(図表番号のつけ方等)が厳密に決まっているため、PMDAのガイドライン準拠が必須です。
サマリー・テクニカル・ドキュメント(Summary Technical Document)<STED>:医薬品を対象としたCTDに対して、STEDは医療機器を対象としています。医療機器規制国際整合化会議(Global Harmonization Task Force、GHTF)」で合意されている形式に基づいて作成され、日本では和訳が中心となります。医療機器は種類が多く、翻訳も多岐にわたるため、翻訳の難易度も高めです。正確かつルールに沿った翻訳が求められます。
■おわりに
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
次回は引き続き「承認申請・製造販売編②」とその他の文書をご紹介していきます。
今回の内容が、皆様の翻訳時にお役に立てば幸いです。
オンラインストアにて添削講座や動画学習サービスを販売中です!
▼医療翻訳学習者向けオンラインストア(M.O.S.)
https://m-t-s.stores.jp/
▼通信添削講座
https://tensaku.m-t-s.jp/
▼動画学習サービス
https://douga.m-t-s.jp
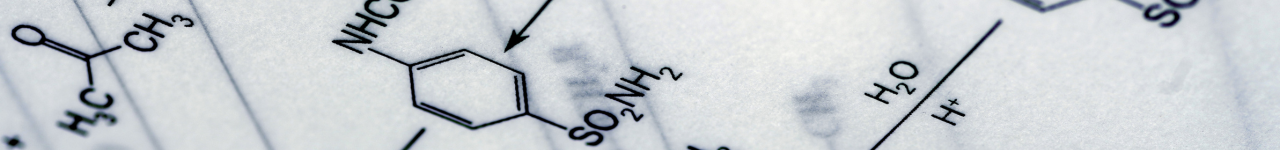


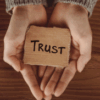
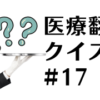
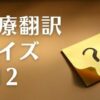
-100x100.png)