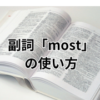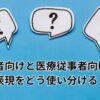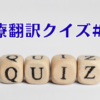薬ができるまでと発生する翻訳文書 ~承認申請・製造販売編②~
前回の「薬ができるまでと発生する翻訳文書~承認申請・製造販売編①~」では、治験終了後に行われる承認申請・製造販売の段階で発生する文書についてご紹介しました。
今回は、その続編として「製造販売」段階で発生する翻訳文書について、詳しくご紹介いたします。
前回の記事はこちら
🔻
https://blog.m-t-s.jp/drug-development-documents3/
■製造販売段階で発生する文書
添付文書(package insert、label/labeling):薬を購入した際に箱の中に同封されている説明書が「添付文書」と呼ばれるものです。添付文書は法律や規制に基づき記載内容や表現方法が定められており、PMDAのWebページから閲覧可能です。(https://www.info.pmda.go.jp/psearch/html/menu_tenpu_base.html)。
翻訳としては、海外で承認された医薬品の和訳、または日本で承認申請された医薬品の英訳(海外展開用)のどちらも発生します。さらに英語以外の言語の翻訳依頼を受けることもあります。文書量は中~小程度で、納期には比較的余裕があります。英訳時はPMDAの英訳ガイダンスの参照が推奨されます。
インタビューフォーム(interview form):添付文書には書ききれない詳細情報を主に薬剤師向けに提供する資料で、すべての医薬品で作成されるわけではなく、日本病院薬剤師会の依頼により作成されます。基本的に英訳で分量は中程度で、納期も比較的余裕があります。
取扱説明書(Information for Use)/ユーザーマニュアル(User Manual):医療機器の使用者(医師や患者)向けに、機器の使用方法などを詳細に記した説明書です。医療機器そのもの(ハードウェア)だけでなく、機器に搭載されるソフトウェアの関連も含まれる場合があり、ITの知識も求められることがあります。多くの場合は和訳で、分量は中程度です。取扱説明書やユーザーマニュアルには「注意」「警告」「~しないこと。~のおそれがある」など特有の文体があり、読者が医療関係者か一般の人かによって表現や用語の使い分けも必要です。
製品説明書:ここで言う「製品説明書」とは取扱説明書とは別に医療機器そのものの特徴や効果効能を説明する資料のことを指します。化粧品の概要を使用者に説明した文書などで、営業や販売時の資材であることが多いでしょうか。翻訳は和訳が多く、分量は比較的少なめで読みやすさが求められます。
製品ウェブサイトやパンフレット:企業の公式サイトや製品紹介パンフレットなど、販売時の資材となるようなものです。ほぼ和訳で、日本語としての自然さや購買意欲をそそるような表現が好まれるため、意訳や調整が必要な場面も多くあります。
プレスリリース:企業が新製品の発表や業績報告などを行う際の広報文書です。和訳と英訳の両方が発生し、納期は比較的短く、翻訳としては情報の正確さと日本語として滑らかさ両方が必要であり、どちらも求められるバランス型の翻訳です。
広告などのマーケティング文書:広告文書やキャッチコピーを含むような資料の翻訳では「トランスクリエーション(transcreation)」(翻訳+創造)」を組み合わせた手法が用いられる場合があります。翻訳+コピーライティングというイメージです。MTSではこの手法自体は扱いませんが、「原文から離れてもいいから、うまい表現にして」というような指示を受けることもあります。原文への忠実さが求められる医療翻訳とは異なり、翻訳者さんの感性と工夫が問われる文書です。
おわりに
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
次回は「(5)製造販売後調査」段階で発生する文書をご紹介いたします。
今回の内容が、皆様の翻訳時にお役に立てば幸いです。
オンラインストアにて添削講座や動画学習サービスを販売中です!
▼医療翻訳学習者向けオンラインストア(M.O.S.)
https://m-t-s.stores.jp/
▼通信添削講座
https://tensaku.m-t-s.jp/
▼動画学習サービス
https://douga.m-t-s.jp
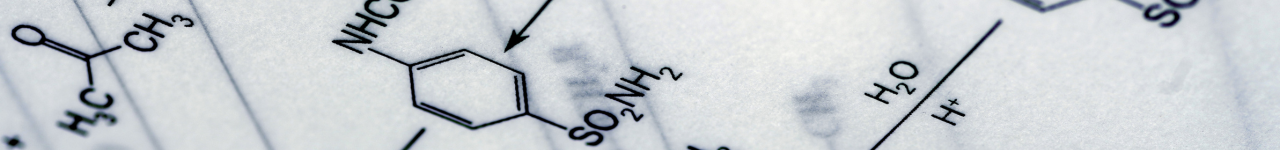


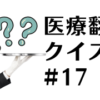


-100x100.png)
-100x100.png)
-100x100.png)